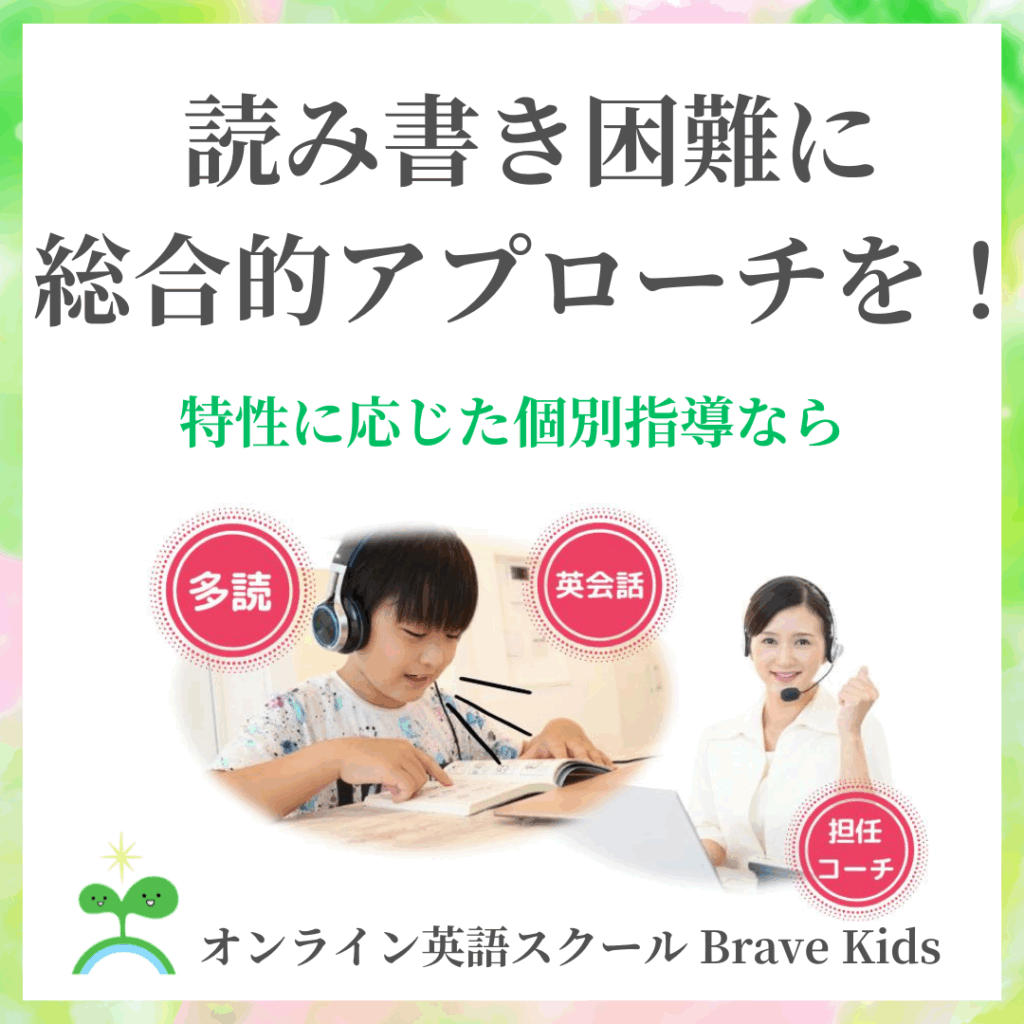中学生で英語の読み書き困難(ディスレクシア)傾向に気づいたらどうする?
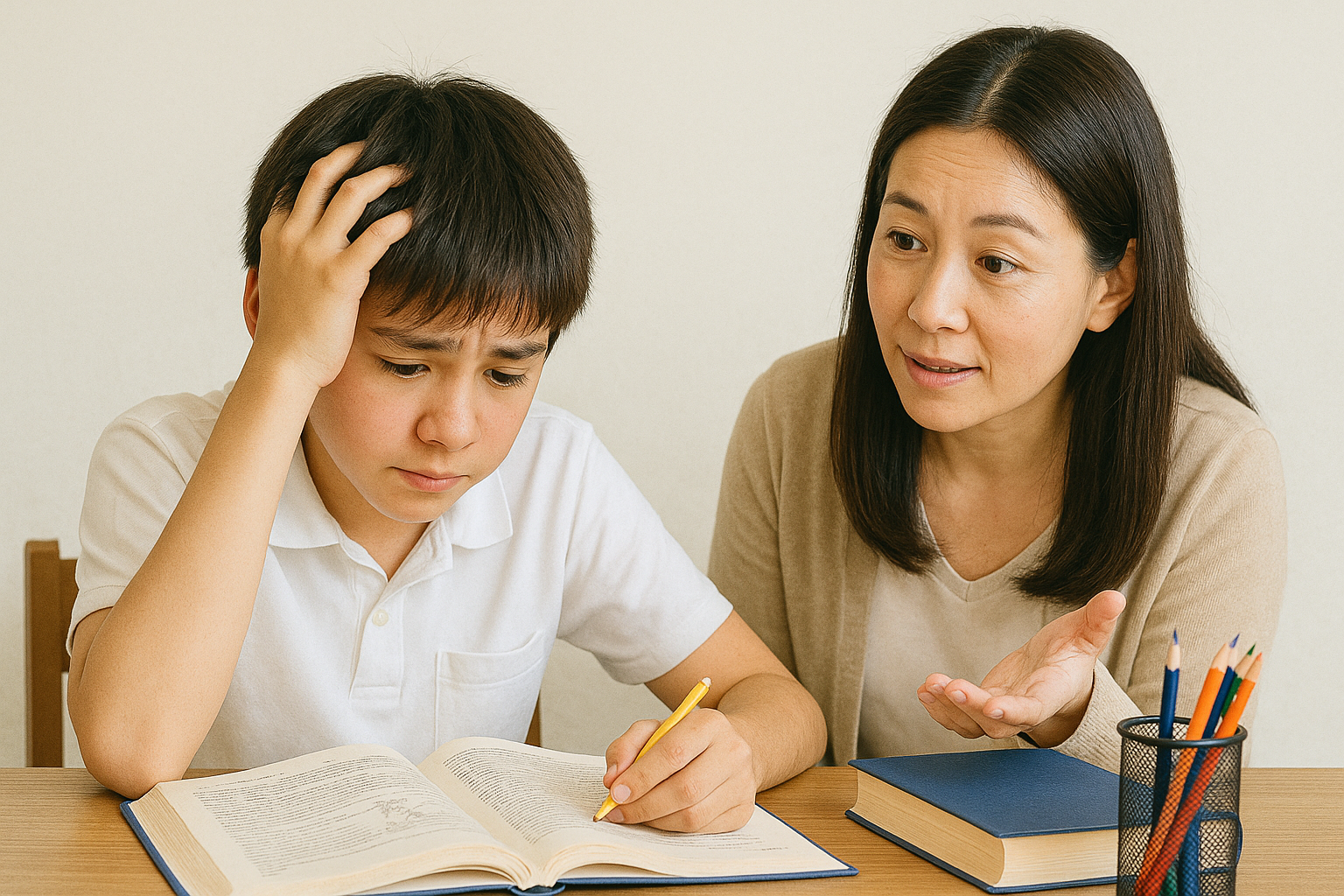
こんにちは!オンライン英会話スクール Brave Kids 代表の上村綾子です。
英語講師として長年子どもたちの学びをサポートさせていただいてきましたが、最近では小児神経科の先生方と連携しながら、英語の読み書きに困難を抱えるお子様や、その親御様のご相談を受ける機会がとても増えています。
英語の読み書きが本格的に始まる中学生以降、学校での単語テストや定期テストの結果を見て、「うちの子、単語がなかなか読めるようにならない」「いくら練習してもスペルが覚えられない」と、気づくケースが決して少なくありません。中には違和感を感じながらも数年が経過し、中学3年生や高校生になるまで有効な手が打てておらず、困り果ててご相談に来られる方もいらっしゃいます。
「ただ英語が苦手なだけ」「英語への努力が足りないだけ」と思っていたら、実は読み書きに困難があり、相応のサポートが必要な特性を持っていたというケースは実はたくさんあります。
この記事では、そういった読み書き困難の兆しが見えたときに、どこからどのようにサポートを始めたらよいのかをご紹介していきます。
どのような読み書きに困難があるのかを確認する
中学生になって英単語が読めない、スペルが覚えられないという悩みを抱えるお子さんの中には、「ディスレクシア(読み書き困難)」の傾向があるケースがあります。まず大切なのは、お子さんがどのような単語でつまずいているのか、具体的に確認することです。
おすすめは、実際に読ませてみること。どの単語でつまずくのか、どのように間違えるのかを観察しましょう。
読めない単語は書けません。まずは読みのスキルを確認しましょう。
yes, not, land のようなシンプルなフォニックスの単語が読めていない場合は、1つ1つの文字がどのような音になるのかという基礎フォニックスから理解できていないということがわかります。
time, loud, right のような2文字以上の組み合わせで音が決まる単語に苦戦している(ローマ字読みしてしまっている)場合は、2文字以上の応用フォニックスの練習が必要だと推測できます。
one, busy, does のようなフォニックスルールが当てはまらない、全体の形で覚えなくてはいけないサイトワードが読めない場合は、サイトワードが壁になっているのだとわかります。
次に、どのような単語が書けて、どのような単語が書けないのかも同様の視点で見ていきます。
基礎フォニックスの3文字程度の短い単語が書けないのか、2文字以上の応用フォニックスが書けないのか、サイトワードが書けないのか。
その時合わせて注意したいのが、単語の覚え方です。単語小テストや定期テスト前に、どのように覚えようとしているのかを観察してみてください。
お子さんが「ローマ字読み」で無理やり単語を記憶している様子がないかを確認しましょう。
たとえば、「come」を「コメ」、「light」を「リグハト」などと覚えてしまっているようであれば、注意が必要です。ローマ字読みは日本語の音に引きずられた間違った方法で、英語の「音」と大きく異なり、このような覚え方は、リスニングやスピーキングで大きな障害になります。
また、単語学習の際に、何回くらいの反復で覚えられるのか、数日後にまだ覚えているかどうかも観察しましょう。
ディスレクシアの傾向が強い場合、文字を書くという行為自体に大きな苦痛が伴う(手が痛いと訴えたり、体が硬直してしまうと訴えるなど)こともよくあります。そのような場合は書いて練習するという機会自体が作れていないかもしれません。
こうした観察を通じて、お子さんのつまずきの傾向や学び方の特徴を把握することが、今後のサポートの第一歩になります。
フォニックス学習は「応用」や「例外」までしっかりと
ローマ字読みで無理やりスペルを覚えてしまうケースはとても多いですし、それをやめさせることは難しい部分もあります。そこで、気づいた時点からで良いのでできるだけ早くフォニックス学習を導入することをお勧めします。
英語のつづりと音の関係を学ぶ「フォニックス」は、ディスレクシアの支援において欠かせない存在です。
フォニックスの学習は、まず「aはア、bはブ」といった1文字単位の基礎フォニックスから始めます。これらはYouTube動画や市販のテキストでも学べるため、最初の導入には適しています。
しかし、本当に重要なのはその先。ディスレクシア傾向のお子さんが最もつまずきやすいのは、2文字以上の組み合わせによる「応用フォニックス」の部分です。
「sh」や「ch」などの子音の応用フォニックスはその中でもまだ覚えやすいのですが、「ou」「ea」「aw」のような母音の応用フォニックスは種類やバリエーションも多く、たくさんの語彙の中で少しずつ定着させるほかありません。
また、「igh」「oul」「ough」など、3文字以上のフォニックスもたくさんありますし、そういったフォニックスルールが当てはまらない例外(サイトワード)も山ほどあり、こういった「量」をカバーするには市販の教材などでは網羅しきれません。
これらのスペルを正しい音と共に一つずつ覚えていくには、個別に対応したフォニックス指導が必要不可欠です。お子さんのつまずきやすいパターンに合わせて、正しい音とつづりを何度も繰り返し学べる環境が必要です。
つまり、一般的な基礎フォニックスをただ一通りやるだけでは不十分。
さまざまな語彙に触れながら、応用フォニックスやサイトワードを少しずつ身につけていける環境が読み書き困難を乗り越えていくカギになります。
知識だけでも不十分。音を伴う多読が必要な理由。
「フォニックスルールを学べば読み書き困難は克服できる」と思われがちなのですが、実はそれだけでは不十分です。フォニックスとは「音から文字への変換ルール」。つまり、出発点は「音」なのです。
文字のルールだけを学んでも、そもそも単語の正しい音を知らなければ、ルールを活用して読んで理解したり、正しいスペルで書くことができません。
たとえば、“night” という単語のつづりを覚えたいとします。このとき、 まず/naɪt/ という音で「夜」という意味になるという音を中心とした単語知識が必要です。そして、iはアルファベット読みの「アイ」と読み、ghは音がない文字であるというフォニックスルールが入ると、正しく読んだり書いたりできるようになります。
とはいえ、毎回 “night”を見るたびに「このフォニックスがこうだからこう読む」と意識してルールを分析していてはスピードが追いつきません。フォニックスを無意識レベルのスキルに落とし込むにはそれなりの「量」が必要となります。
多聴多読を通して、文中で何度も「音と文字のセットで」目にすることで、無意識レベルでフォニックスルールを適用し、/naɪt/とパッと読めるようになります。
英語の全単語のうち約3〜4割は、フォニックスのルールに当てはまらない「サイトワード」と呼ばれるものです。これらは、例外の塊であるため、音とスペルの対応では覚えられず、やはり文中で何度も目にして「形」として覚えていく必要があります。
そのため、読み書き困難を軽減させていくために「音を伴う多読」が有効となります。
正しい音声付きのテキストを何度も繰り返し読むことで、自然と音とスペルが結びつき、形として記憶に残ります。
こうした反復経験の蓄積が、ディスレクシア傾向のお子さんの読み書き能力向上には不可欠なのです。
中1の基礎文法をとにかくしっかりと!
読み書き困難のお子さんは、単語のスペルだけでなく、文法でも早い段階でつまずくことが多くあります。
be動詞と一般動詞を区別しながらの文法操作や、単数・複数の扱いなど、中1の前半で習う最も基本的な部分でつまづいてしまうというケースです。
学校や塾では文字による文法習得が中心のため、読み書きに困難があると文法学習にも支障が出てしまうというわけです。
このときもやはり、文字による学習に頼りすぎるのではなく、「音」を活用することが大きな助けになります。文法問題といえば選択肢から正しいものを選ばせたり、ランダムに並ぶ語順を正しく並び替えたりという、紙の上での練習ばかりですが、そうではなく「この英文を聞いて間違えを直してみよう」「・・・という文章を英語で言ってみよう」のようにリスニングやスピーキングの中で文法を練習する方法も大変有効です。
読み書き困難の特性が出にくい「音」を活用した学習方法も活用しながら基礎文法をしっかりと固めつつ、フォニックスを少しずつ習得していくことで、読み書きで正しい文法を活用できるというところに少しずつ近づけていきます。「読み書きが苦手だから読み書きから練習する」ではなく「読み書きにつながるように、まずは音から学んでいく」という「逆転の発想」が、遠回りに見えて実は一番確実な方法となります。
文法を口頭メインで学ぶ際には、日本語での解説を交えてくれる「バイリンガル講師」がいると、理解が格段に深まります。基礎文法であっても操作は意外と複雑です。オールイングリッシュでの説明や理解には限界があります。
フォニックス指導も文法指導もでき、正しい発音で正確にスピーキングができるバイリンガル講師による総合的な指導が、文法運用力はもちろん、読み書きの土台づくりに非常に有効です。
気づいた「今」スタート!中学のできるだけ早い段階で支援を始めるべき理由
英語の読み書き困難に気づいたら、なるべく早く対策を始めることが大切です。
特に中学1年生の1学期は、「英語が得意になるか、苦手意識を持つか」の分かれ道です。
学校で本格的なテストも始まるため、気づいてあげる機会としては最適です。ここで放置してしまうと、その後ずっと授業についていけず、自信を失い、さらに英語が嫌いになってしまうという悪循環に陥りかねません。
オンライン英会話スクール「Brave Kids」では、このようなお子さんにぴったりのサポートを提供しています。まず特徴的なのが、毎日たった10分、楽しい「ドラえもん英語版」を使って、シャドーイング(音マネ)と多読を組み合わせた学習法。これにより、正しい音とスペルを紐付けならが、毎日コツコツと「量」をこなしていくことができます。
さらに、担任制の個別指導で、ひとりひとりのつまずきや強みを把握しながら、4技能(聞く・話す・読む・書く)+フォニックス+文法をバランスよく指導しています。お子さんの特性やペースに合わせて、無理なく継続できる学習環境が整っています。
書く作業自体に苦痛を伴う場合は、タイピングでライティング練習や文法練習に取り組んでいただくこともできます。お子様にとって一番困難が表出しにくい方法、一番楽しく無理なく続けられる方法、そして確実に成果を感じられる方法を担任コーチと一緒に相談しながら最善の学習方法を見つけ出していただくことができます。
英語がうまく読めない、書けない――そんな我が子の姿に戸惑い、不安を抱える親御さんも多いと思います。
でも、大丈夫!英語ディスレクシアの研究は少しずつ進んでいます。
学校教育現場ではまだまだ英語読み書き困難への対応が進んでいるとは言えない状況ですが、ICT教育の発展で、読み上げ機能の活用、タイピングでの回答など、読み書き困難の特性を乗り越えていける可能性の光も見えてきています!
実際、私と小児神経クリニックの先生とでディスレクシア傾向を判断し、医師の意見書を学校に提出することで、学校における英語学習環境・試験環境を整える取り組みをされている親御様たちもいらっしゃいます。
ぜひ Brave Kids と一緒に、長期的視野を持ちながら、決して焦らず、お子様の様子を丁寧に見ながら、より良い英語との関係を作るサポートをしていきませんか?
気づいた「今」が、未来を変える第一歩です。ぜひ一度、Brave Kidsの無料体験を試してみてください。
| 読み書き困難に対応!オンライン英語スクール Brave Kids! |
| ▼Brave Kids の特徴 1.英語版「ドラえもん」の多聴多読で、音を伴う語彙知識が増える 2.バイリンガル担任コーチが、フォニックスや文法も個別指導 3.文を組み立ててスピーキングする力も個別指導 4.毎日10分の動画学習、動画添削、ZOOMレッスンと網羅的カリキュラム 5.タイピング活用などディスレクシア傾向にも個別対応 他のスクールにはない特別なカリキュラムをまずは体験受講でご体感ください! |
| Brave Kids 体験受講はこちら |